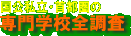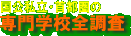| 調査 |
平成12年度 学校基本調査報告書の分析
〜第4分野(衛生)編 |
|
|
入学者数は4年度の1.5倍、4万2367人に拡大。「美容」「その他」と「栄養」「調理」「理容」の二極分化へ
前号に引き続き、専門学校を分野別に見ていく。今回は第4分野の衛生を見てみたい。データは、文部省の「学校基本調査報告書」の50分類によるもので、この資料をもとに平成に入ってからの12年間の定員数・入学者数を中心に、その推移を分析する。
▼分野全体では安定した増加傾向
前号の第3分野(医療)同様に、第4分野(衛生)は多くが国家資格関連学科である。第3分野と同じようにこの分野もまた、専門学校全体の入学者数がピークとなった平成4年度以降もなお上昇を続けており、根強い人気がうかがえる。次ページからの表は専門学校全体の入学者数が最も多かった4年度を100として計算したものである。
衛生分野全体の入学者数を見ると、12年度には4年度の約1.5倍(4年度27,306人→12年度42,367人)に拡大している。専門学校全体の入学者数が減少している中、前号で見た第3分野同様、この分野の動きは異質な動きといえる。充足率も、第3分野ほど高くはないものの、資格取得への強い関心から他の分野と比べて高く、就職氷河期に突入していった5年度以降も80%〜90%台を維持している。
この分野は、かつては「調理」が最大で、平成元年度では全体の42.8%を占めていた。以下、「美容」(30.4%)、「栄養」(15.3%)、「理容」(6.7%)、「その他」(4.8%)であった。その後、この割合には大きな変動があり、12年度では、トップが「美容」で(46.5%)、以下、「調理」(31.7%)、「その他」(9.1%)、「栄養」(7.8%)、「理容」(4.8%)となっている。
「理容」・「美容」、「調理」の法律改正の他に、「栄養」の大学・短期大学移行などの影響が大きい。また、グルメブーム、ヘアメイクやエステティック、ネイルアートなど若者のおしゃれへの関心の高まりなども大きく影響しているものと思われる。特に、この若者の志向の変化が、「その他」を大きく押し上げているといえる。
以下、文部省の分類にしたがって、各分類ごとに動向を見てみよう。
★401 「栄養」
「栄養」は、分野全体が拡大傾向にあるなかで、「調理」「理容」と共に若干の縮小傾向を近年示すようになっている。6年度までは、他学科と同様に拡大傾向にあったが、6年度をピークに減少傾向へと一転し、6年度ピーク時の65.7%の規模に縮小している。これは、大学や短期大学へ専門学校の栄養科が移行したことに伴う一時的な傾向という要因もある。しかし、減少は続けているものの、10年度以降は減少率も小幅となっており、入学者数3,300人ほどの規模で安定しそうな雰囲気が感じられる。
「栄養」は、栄養士資格の取得が目的の学科であり、若者のライセンス志向だけに焦点を当てれば順風のはずである。しかし、入学者数の推移を見るかぎりでは、単に大学や短期大学への以降という要因だけではなく、この社会の順風に乗りきれていないという側面もある。
現在、栄養士の数は過剰気味といわれており、せっかく、栄養士資格を取得しても、必ずしも就職できるとは限らない。資格イコール就職という図式が成り立つ場合においてのみ、資格取得へのメリットは生まれる。従って、国家資格取得ができる学科、というだけのアピールでは、その資格を生かした専門職種に就けない可能性が高い以上敬遠する人が増えるのはやむをえないともいえる。
栄養士資格は、専門学校からの移行組も含めて、大学や短期大学でも同種の学部・学科が多数設置されている。そのために、これらの学部・学科との競合も大きな障害となっている。
近年、「健康」「スポーツ」「福祉」「医療」などへの社会の関心が高まり、専門学校でもこれらの知識・技能を身につけた栄養士を育成するようになっている。こうした時代にマッチしたカリキュラムへの柔軟な対応を見守りたい。
★402 「調理」
「調理」は、4年度以降も順調に規模を拡大し、8年度にはピークとなった。しかし、その後は減少を続け、ピーク時に比べて、17.1%、実数では2,763人もの大幅な減少となっている。
充足率をみると、7年度100.2%、8年度97.8%と好調だったが、以後は、定員数は1万7000人台で安定しているが、入学者数の減少傾向は変わらずで、充足率は年々低下している。
好調だった頃の「調理」の人気は、バブル経済期から続いたグルメブームが支えていた。しかし、そのブームもここ数年は落ち着きを見せはじめ、ブームに押されて増え続けていた入学者数にも、ブレーキがかかりはじめたといえる。
「栄養」と同じように、「調理」もまた、資格取得を特徴に掲げるだけでは入学者を集めることができにくくなってきた。そろそろこうした資格中心の教育内容を見なおす時期にきているのではないか。
街にはファミリーレストランをはじめ、チェーン店のレストランが増えている。これらのレストランでは、メニューを開発する独創性や経営的センス、極端に高度な技術をそれほど必要とはされず、免許を持ってさえいれば調理人として務まるようなところも少なくない。
一方では、客単価1万円以上という高級志向のレストランも出始めている。当然のことであるが、これらのレストランで要求される調理人への期待と要求は高い。
2年制の「調理」系学科では、1年制ではカバーしきれない高度な技術や経営的センスを磨くためのカリキュラムを授業に組み込んでいるところもある。社会の中で外食産業は大きく変わろうとしている。調理師を目指す人たちにとって、魅力ある学科とはどんな学科なのか、もう一度根本から考え直すときが来ているのではないだろうか。
★402 「調理」
「理容」は、平成に入ってからの12年間だけでも、4年度が入学者数が最も少ないという他には見られない推移をたどっている。表にはないが、昭和62年度の入学者数は2,593人で、これ以降、4年度まで減少、再び8年度まで増加をし、以降は減少と増加を繰り返している。
「理容」は、理容師資格の法律の改正によって、インターン制度が廃止され、10年度から2年制になり、課程を修了すると直接国家試験の受験資格が得られるようになった。これにより、入学者数が大幅に増加するのでは、という期待感があったものの、10年度は前年並み、11年度には大幅な減少、12年度は11年度並みとなっており、法改正が必ずしも入学者数の増加にはつながってはいない。
要因の一つには、「理容」のピークとなった8年度まで、同じような動きを見せていた「美容」への入学者の流出が考えられる。「理容」がここ5年間、増減を繰り返している一方で、「美容」は大幅に入学者数を増やしている。男性は理髪店を、女性は美容室を利用するという、ある意味での住み分けで共存していた「理容」と「美容」だが、このイメージが崩れ、男性でも美容室へ通う人が増えている。それを考えると、「理容」が「美容」に押されてしまうのも無理はないといえる。
しかし、「美容」との共存をもう一度図るためにも、「美容」にはない、「理容」独自の特色を打ち出し、美容師とは異なる理容師育成をアピールしていく必要があるのではないだろうか。
★404 「美容」
4年度から増加傾向にあり、12年度まで規模を拡大し続けているのが、「美容」である。平成の12年間で最も入学者数が少なかった3年度の入学者数と比較して、12年度は約2.5倍と急拡大している。さらに7年度以降は、いずれの年度も定員を上回る入学者数となっており、12年度では、1,761人の定員オーバーとなっている。
学校・学科数も勢いよく増えつづけている。新設校だけでその増加をみると、10年度12校、11年度8校、12年度12校(いずれも各種学校から専修学校への移行を含む)に、「美容」を持つ専門学校が新設されている。これら以外の既存の専門学校で、学科増設という形で新設されているケースもある。
法律改正で、専門学校で2年間の課程を修了すれば受験資格が得られるようになったことも一つの要因ではあるが、それだけではない。特に若年層の「美」への関心の高まりは強く、その範囲もさらに広まっている。従来の美容師というと、ほとんどの人が美容室を活躍の場としていたが、現在は、エステティックをはじめ、ネイルアート、メイクアップなどの専門サロンが誕生しつつあり、その活躍の場も多様化している。しかし、この関心の高さが、一時的なブームである可能性は否定できず、ブームが去った後、どうなるかという不安もなくはない。
★409 「その他」
「その他」には、製菓、製菓衛生が含まれており、この「その他」の中で大きな割合を占めている。この12年間で最も入学者数が少なかった4年度と比べて、12年度の入学者数は約3倍に上っている。
また、4年度までは男女比ほぼ50%と同じ比率だったが、5年度以降は女子の割合が高くなっている。12年度には76.8%となり、圧倒的に女子の割合が高くなっているのが特徴的だ。
▼流行に左右されない柔軟性を
栄養士、調理師、理容師、美容師、製菓衛生士と資格に直結する学科がほとんどのこの分野は、第3分野同様に、根強い人気を誇っている。特に、この分野で目指す職種は、資格取得後には趣味と実益を兼ねられ、努力と実力次第では独立という大きな夢の持ちやすい分野でもある。そのため、高校卒業者だけでなく、幅広い年齢層がこれらの学校・学科へ入学するようになっているのも大きな特徴だ。しかも、「栄養」を除けば、大学や短期大学の学部・学科との競合もなく、専門学校の独壇場といえる強みもある。
既に再三述べたように、ブームという追い風が、この分野の人気を支える形となっている。しかし、2本柱の一つである「美容」は順調に拡大を続ける一方で、「調理」はブームに陰りが見え始め、その影響が入学者数に現れるようになってきた。つまり、この分野は流行に左右されやすい分野なのである。では、流行に左右されにくい学科にするためにはどうしたらよいか。
現状のカリキュラムを社会のニーズに合わせて改革することに尽きる。「法定科目の消化だけで手一杯」という声も聞こえてきそうだが、学生の学ぶ目的が、著名企業への就職なのか、独立なのか、あるいはそれ以外なのか、をもう一度考えたい。取得できるのだからと、ただ漠然と免許取得をめざすより、明確な目標を持っていた方が、学生の意識は高くなるし、知識や技術の取得も早い。
社会の動きに柔軟に対応したカリキュラムが自在に組める、これが専門学校の最大の特徴である。「栄養」を除いては大学や短期大学とのバッティングのない分野であるという特性を最大限に発揮した教育を期待したい。(伊藤)
『専門学校在学者の実態と意識に関する基礎的、総合的な調査研究報告書』(関口義先生:京都文教大学教授)に見る専門学校入学にさいしての県内進学と県間移動
昨年の本誌11月号で関口義先生の研究報告書のなかの一部、専門学校生の県間移動を紹介した。これは『学校基本調査報告書』のデータをもとに、関口先生が独自に推測、考察されたものであった。
今回、関口先生はさらに『専門学校在学者の実態と意識に関する基礎的、総合的な調査』(対象学生は全体で5万2,791人)を実施し、先ほどその報告書が刊行された。今回の調査では、専門学校入学者の出身高校所在地の都道府県名欄を用意して、その都道府県名を記入してもらうという新しい試みがなされ、対象学生5万2,791人の県間移動についての報告があるので、11月号で紹介したものと比較しながら、県内進学と県間移動についてもう一度見てみたい。
■北海道・東北
推測(11月号、以下同じ)では境界パターンに区分された北海道は今回の調査でも同様だった。流入出とも多くなく、道内進学者が多い。
東北では、推測どおり宮城を除く5県が流出パターンである。今回調査においても流出先は、同じ東北内の宮城、次いで東京が多く、埼玉、神奈川などへの流出も少なくないことが分かった。東北他県の流出先となっている宮城は、これら5県からの流入が他に比べて多い。わずかながら流出者もある。流出先は東京を中心とした首都圏のほか、同じ東北では山形が多い。
■関東1(北関東3県)
県内進学者のために専門学校が発達してきたが、東京などへの首都圏への進学者も多い、と推測された。
3県からの流出先で一番多いのはやはり東京だった。その他では栃木から埼玉や群馬への流出が目立つ。流入では茨城の場合は東北から、群馬の場合は隣接する栃木と埼玉と長野の3県が多くなっている。3県のうち、栃木は他県への流出者数が県内進学者数を上回り、他の2県は県内進学者数より流出者数の方が少なかった。そのため栃木は典型的な流出パターンとなったが、茨城、群馬は推測とは違って流出パターンとはいいきれないという結果となった。
■関東2(首都圏1都3県)
推測と同じく、東京は流入パターンだった。他の道府県すべてからの流入があり、隣接する埼玉、神奈川、千葉からの流入が特に多くなっている。これらに次いで多かったのが、順に茨城、静岡、長野、新潟、栃木となっている。
東京への流出規模が大きいと推測された埼玉の場合は、他県への流出だけでなく他県からの流入も多かった。流入先は、東京、栃木、群馬、茨城、神奈川と関東各県が中心となっており、それ以外にも静岡、長野、福島などからの流入があるため、流出パターンとはいいきれない結果となった。
千葉、神奈川では県内進学者より、東京への進学者が多くなっており、推測と同じ流出度の高い県であるという結果が出ている。神奈川では東京、静岡などからの流入も少なくないが小規模にとどまっている。千葉は著しく他県からの流入が少なかった。
■中部1(北陸3県)
いずれも県内進学が多く、他県からの流入が少ないという、推測に近い結果だった。推測では石川のみが境界パターンだったが、3県ともこれに近い。福井では特に流入が少なく、今回の調査では4県(石川・岐阜・滋賀・京都)からの流入しかなかった。流出では東京のほか、愛知、京都、大阪が多くなっている。
■中部2(甲信越・東海)
名古屋という中心都市を抱える愛知は推測と同様に流入パターンで、岩手を除くすべての県からの流入がある。多い順に、静岡、長崎、長野、北海道、熊本となり、隣接する岐阜、三重からの流入は思ったほど多くなかった。
三重、岐阜、山梨、長野の4県が、推測同様に流出が多いパターンだった。流出先で最も多いのは、長野の場合は東京、岐阜は愛知、三重は大阪だった。また意外にも山梨は北海道への流出が最も多かった。
新潟と静岡は、推測どおりいずれも県内進学が多いが、新潟では東京への、静岡では東京と愛知への流出も少なくない。
■近畿
西日本の中心地である京都・大阪が、推測と同じく流入パターンであった。流入先も推測と同じで、大阪では順に、兵庫、京都、和歌山、奈良から、京都の場合は、大阪、兵庫からの流入が多い。
滋賀は流出規模が大きいとされたが、調査によると流入も多いことが分かった。特に京都からの流入があり、流出と相殺されるような形になっている。
和歌山では、県内進学者より大阪への進学者が多かった。推測どおり、流入が極端に少なく典型的な流出パターンとなった。流出優位と見られた兵庫は、大阪や京都流入があり流入も少なくなかった。県内進学が多く、流入も少なくないと推測された奈良も同様に大阪や京都からの流入があり、どちらも流出パターンとはいいきれない結果となった。
■中国
広島は推測と同様の結果で、県内進学者が多く、若干ではあるが流出者より流入者が多かった。流入先の多くは、島根、岡山、山口となっている。流出者が多いと推測された鳥取もまた流出者より若干流入者が上回っている。岡山では推測同様に、流入者は少ないものの県内進学者が多かった。
島根と山口は推測通り流出者が多い。いずれも広島と京阪神地区への流出が多く、加えて山口では福岡への流出も少なくない。
■四国
4県とも流入者より流出者が多いという点では推測どおり。近隣の四国内や中国よりも京阪神地区への流出の規模が大きい。 流出者が多いものの、徳島と高知では、県内進学者が比較的多く、流出者を上回った。推測では高知のみ自県充足型とされたが徳島もこの型に入る。他の2県は推測どおり典型的な流出パターンとなっている。ちなみに愛媛では他県からの流入が今回の調査対象者のなかにはまったくいなかった。
■九州
推定では流入パターンに数えられていた福岡だが、県内進学の割合が高くなっており、流入パターンにまではいたらなかった。ただし、流出者に比べ流入者が上回っており、その先は九州の他県と山口が目立つ。流出では隣接する佐賀と京阪神地区が多い。
その他、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、沖縄では、流入者に比べ流出者の数が多いが、推測されたとおり県内進学の割合が高い。
九州では長崎のみが、大幅に県内進学者と流入者の合計が流出者が上回った。流出先は福岡を始めとして隣接県を中心に、その他では愛知への流出も目立った。(伊藤)
|
|
|
|